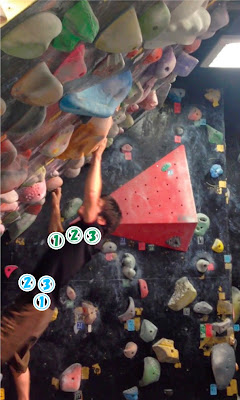疲れている。
体がそう強く訴えかけていた。
シフトの関係上、6/14~6/15が二連休だったのだが、
6/13の夜時点ではこの連休はもう寝て過ごすべきだと思っていた。
6/14の午前1時に就寝したのだが、そのままぐっすりと午後1時まで眠った(12時間!)。
起きてもまだ疲労は身体にこびりついており、それを拭うべく、起きてすぐたっぷり食事をして、昼から長い風呂に入った。
そして自室でごろごろとしていると午後7時再び眠りに落ちた。
次に目が覚めたのは6/15の午前1時だった。
その時異変に気付く。
全く疲れていなかった。
あれほど身体にしつこくこびり付いていた疲労が嘘のようにすっかりと消えていた。
深夜だと言うのにまったく眠気もなかった(当たり前だが)。
今すぐにでも登りに行けそうだ
と思った。
と思ったあと、いや、実際にそれもいいかもしれない、と考えた。
今から準備をして少し遠いエリアに車を走らせれば到着するのは早朝。
涼しい環境で登れるんじゃないだろうか。
それで暑くなってきたら帰ってくればいい。
そして、
そういえば戸河内に忘れ物があったなあ
と思い出す。
そんなこんなで6/15午前5時30分
僕は
戸河内に居た。
狙い通り、早朝の空気はひんやりと澄んでいて、岩のコンディションも悪くない。
早速「忘れ物」であるところの
イカヅチ(二段)
を落としにかかる。
アップがてらムーブを改めて確認し、
登れた。
そら(雨の日にゴール手前まで行けたんだから)そう(乾いてれば登れる)よ
主目的を済ませたわけだけど、まだまだ
朝6時過ぎ、まだまだ世間は起きだしてもいない。
じゃあ次に、と
イカヅチの直登ver.である
カナヅチ(初段)
にトライ。
いや、初段にしては悪い!
とはっきり思う。
イカヅチと4手目まで共通であるわけだけど、その4手目までがイカヅチのワルいところなわけだし。
そして5手目もなんだか悪い。ストライクゾーンが狭くかつ奥まっていて何度か外してしまった。
これは人によってはイカヅチよりもカナヅチのほうが苦手って人も居るんじゃないかな。
ラインもこっちのほうがカッコイイような気がする。
さてまだまだ時間はたっぷりある。
お次は
レスキュー返し(初段)
以前登ったモスランジと同じスタートから逆方向へ登っていく感じ。
カチ握ればいいだけのシンプルな課題。
実は意外とてこずった。
イカヅチ、カナヅチと打ち込んだ直後にいきなり登ろうとしたのが悪かった。
やはり一人だとレストをする気にならんからな。
意識的にちゃんとレストしたらすんなり登れましたとさ。
さてそろそろヨレてきたところで
次は
ノロ(初段)
まずコイツについて言うことは、スタート位置が高すぎだってこと。
チビの僕にはスタート位置につくのがちょっとキツかった。
一人で来てるわけだから当然マットも1枚しかないからマット積むってことも出来ず。
まあ課題自体は、カチ握って直登!っていうこれまたシンプルな作り。
指にヨレを感じて少し不安だったけどこの程度の課題で敗退するわけにはいかんわな。
この時点でそろそろ気温がだいぶ上がってきた。
そしてもう一つ問題が。
実は僕戸河内のトポ持ってないんですよね。
これまで登った課題はすべてラインを人づてに教えてもらったもの。
そう
もう知ってる段課題が無くなってしまった(ノロをSDにすれば三段になるけど結構ヨレてるのに三段やるってのもなあ)
幸いスマホ圏外ではなかったのでその場で調べることが出来た。
スマホ片手にうろついてみると
メカキングギドラ(初段)
という課題を発見!
小さめな岩なのでヨレている状態でも危険は少なくて丁度いい!
決して難しい課題じゃなかった。
たぶん内容としては今日登った初段の中で一番簡単だったんじゃないかと思う。
が、思いのほか苦戦。
ムーブは簡単に出たけどつなげようとすると腕がロックを拒否する。
いやーヨレてた。でもなんとか気合で登った。
と、
ここでそろそろ正午になろうとしていた。
気温もかなり上がっていて、汗はだくだく止まらない。
2リットル持ってきていた飲み物もとっくに無くなっていた。
筋肉に強く力を込めるとすぐにその箇所が攣ろうとする。
うん、ここらで潮時かな、結構課題落とせたし(計6段)現状もう落としたい課題も無いし。
ということで帰宅。
日が沈む前に帰ってこれた。
今回突発的にこんな岩行をしたわけだけど、
いや、これからの季節
ほんとにこのプランは悪くないかもしれない。
夜のうちに出発→早朝~午前中登る→暑くなったら帰る
の流れ。
まああとはあれか
身体の声を聞け、ってことか。
調子いい!行けそう!っていう体調の時はまあ大体実際行けるもんなんだな、と。